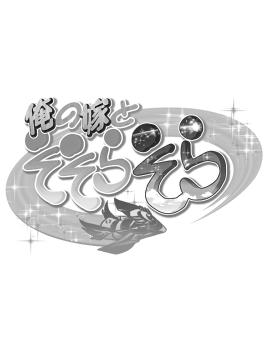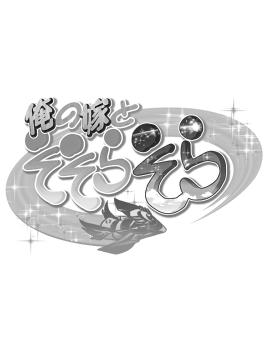プロローグ
アカディミア学生【ソラ・リュミアート】は困惑していた。
「だって、だってもうすぐ……」
寝言のようにモニョモニョと前置きして、彼女はくわと目を見開く。
「もうすぐ、バレンタインだっていうのに!」
バネ仕掛けみたいにベッドから身を起こし、寝ぐせでツノみたく立った前髪も直さずソラは声を上げたのだ。
ちなみに時間は朝の六時だ。部屋の中でも息が白くなるくらい寒い。
「おはよう。ところで、話が見えないんだけど」
彼女のアニマ【ミィ】が姿を現し怪訝な顔をした。
「わからない? この私のアセりが」
首を振るミィに向かって、ソラはバタバタと手旗信号のような身振り手振りをまじえて述べる。
「気がつけばもうバレンタインシーズンなんだよ! 地上があったころからレンメンとして続く伝統行事の!」
「ああ、まあ、そうね。そういやもうじきね」
それで? とミィは腕組みする。ミィも寝起き感を出しているのかパジャマ姿だ。
「ミィは知ってる? いにしえのオークマスター『大セレナ』が従者のゴブリン『アルテア』とともにチョコの木の種を荒野に埋め、愛を知る人に幸せあれ、と三日三晩祈ったところ木が一気に成長してチョコレートの起源になったという伝説を」
「あのね、それいわゆるおとぎ話でしょ? だいたいなによ、『愛を知る人に幸せあれ』って。あと、チョコの木じゃなくてカカオだと思う」
「伝説がホントかどうかは関係ないのっ」
と声を上げたとき、ソラはベッドに仁王立ちになっていた。
「大切なのは、いま私が『プレゼントはチョコがほしいなー』って思ってるってこと!」
そんなことだと思った、と、ミィは渋柿をかじったような顔をして肩をすくめた。
「チョコの場合、たいていは女の子が送る側じゃないの?」
「でも欲しいんだもん!」
「子どもか!」
なお、見た目に限ればミィのほうが断然幼女だったりする。
「……くれないの?」
ミィは「あのねえ」と前置きしてから言った。
「とっくにネットで注文してるから、バレンタイン当日には配達されると思うけど」
うっほーい、とソラは踊るのであった。それも、子鹿のように小刻みなステップをタイミングよく順序だって踏むという本格的なやつを。
「アニマからチョコ送ってもらってなにがそんなに嬉しいんだか……」
やれやれ、とミィは苦笑いするほかなかった。ソラが特別な誰かにチョコを送ったり、特別な誰かからバレンタインカードや花束を贈られる日は、まだまだ想像すらできなかった。
★★★
……なんていうバレンタインもあるだろう。
もっと熱々のバレンタイン、くすぐったくなるほどスイートなバレンタイン、あるいは逆に、スリルとアドベンチャーに満ちたバレンタイン、はたまた、せっかくの一日が仕事でつぶれるバレンタインなんてのもあるかもしれない。
あなたとあなたのアニマはその日、どんな一日を迎えることになるだろうか。
『こんな風に過ごしてみたい』
『あんなところに行ってみたい』
『アニマから思いがけずそんな話が出る、なんて展開がいい』
『第三者があらわれて色々大変な一日を……』
などなど、あなたが考えるあなたとアニマらしいアクションプランを、がつんと威勢良く、あるいはそっと気恥ずかしげに、いずれにせよ遠慮なく送っていただきたい。


解説
個別記述が基本となる日常系シナリオです。
ひろく『愛』にまつわる風習が『のとそら』世界には根付いています。
現代日本のバレンタインのように、女性が意中の男性にチョコレートを送るという文化もあります。ですがそれに限らず、恋人や親しい者同士で花束やカード、アクセサリーを送りあうという文化も定着しています。
なので話は恋愛に限りません。日頃お世話になっている人や友達、あるいは上司(?)に感謝の気持ちを届けてもいいのではないでしょうか?
あるいは、バレンタインなんて関係ねーぜ、と孤高(孤立ではない)を貫くという姿勢もよいでしょう。バレンタインから離れる真冬の一日なんてのもオツですよ。
こんな一日を過ごしたい。
こんな会話をアニマと交わす。
こんな場所に出かけてみる。
などなど、あなたらしいバレンタインの過ごし方を教えて下さい。
ゲームマスターより
よろしくお願いします。マスターの桂木京介です。
あなただけのバレンタインを描いてみませんか?
本エピソードは、そのお手伝いをします。
本作は【終末世界のバレンタイン】ミニエピソードキャンペーンの一作となります。
自由度の高いエピソードにしたいので、『日常』ジャンルにはとらわれなくて構いません。
ハートフルでもエキサイティングでも、はたまたホラー(バレンタイン当時に浮気がバレる……というのはなかなかホラーな展開でしょう!)でも、幅広く対応させていただきます。
NPCの【ソラ・リュミアート】はもちろん、【フラジャイルのマリア】【リン・ワーズワース少尉】、【あなたがいきなり考えた新NPC】など、世界観から極端に外れない限りはどんなNPCを呼ぶこともできますので、試してみるのも一興ですね。
それでは次はリザルトノベルでお会いしましょう。
桂木京介でした。
|
vD:だって、だってもうすぐ…… エピソード情報
|
| 担当 |
桂木京介 GM
|
相談期間 |
3 日
|
| ジャンル |
日常
|
タイプ |
EX
|
出発日 |
2018/2/22
|
| 難易度 |
とても簡単
|
報酬 |
なし
|
公開日 |
2018/03/03 |
|
|
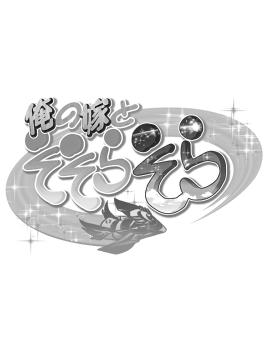
|
*呼びたいNPC:潮 綾 エクスがいつの間に連絡を取ったのがきっかけで街で一緒に過ごす事に 来てくれたら、色々話をしつつレストランへ行く 今はバレンタインフェアでチョコ系のデザートが安く食べられるから、好きな物を食べてもらおう その後は街を散策しながら、エクスのオススメらしい装飾品店へ行く そこで見つけた、どんな服装でも合いそうな小さくてシンプルな花の髪飾りをプレゼントする せっかくのイベントだし、その記念って事でいいから遠慮せずに受け取ってほしいな? 帰る時は家まで送る。綾なら変なのに襲われても返り討ちにしそうだが、せっかく来てくれたのに街でお別れってのも味気ない それに、今日楽しめたか感想も聞きたいしな
|
|
|
|

|
昔、母様がバレンタインにクッキーを焼いたのを思い出した 僕と父様はこっそり扉の陰からのぞいて見てたんだ スピカの提案でメイド達にクッキーを焼いてもらうことに 昔話も出て懐かしい気持ちになる スピカ飴欲張りすぎ。でも綺麗なグラデーションになると思うよ クッキーは美味しかった 残念ながら母様の思い出のクッキーからは程遠いよ あの味は真似できない。だって……塩が入ってたんだから! 気づいた母様は止めたけど、父様と2人飴の部分をなめながら食べたんだ 母様もクッキーは作れない人だったよ でもあの時の事は僕の中では「楽しい」のカテゴリに入ってる ……2人が亡くなった後、こんな風に思い出話をする事がなかったから 楽しかったよ
|
|
|
|

|
フラジャイルのマリアよ。 君の記憶の中にもバレンタインというイベントは存在したのか? …いや、今一つ由来がわからないものでな。 そもそもチョコレートとは今のように菓子であったのか… 保存性、携行性に優れ、カロリーの補給にも向くこの食べ物は元は戦場で食べられていたのではないだろうか。 実際僕も非常時に備え幾つか確保している。 そう考えるとその由来にも何やら物騒な起源があるのではないのか、と僕は思うのだ。 それは兎も角。食べ物は美味いほうがいい。 この時期は多様なチョコレートが売り出されるのでな。店によっては限定品などもある。 人手がいるのだ…街に出るついでで構わん、手伝いを頼みたい。どうだろうか?
|
|
|
|

|
心情 バレンタインにチョコって…かなり理に適っているよねー 昔はカカオなんて高級なもの過ぎて、耐性ない人はすぐ血糖値が上がるんだもん それを恋と誤認させるって…狙っていたのなら考えた人あったまいー さてさて今回はどんな風にたのしもーかな 行動 すごくすっごく悩んだ結果!バレンタインは普通にお菓子作りになった!わーい!ぱちぱち チョコって健康にもいいらしいから、知り合いに配るのもありだなーって思って…ついでに子どもとかにてきとーに渡そう! 元気になるようにドーピングクッキングで作って…え?駄目?じゃあ、しょうがない、普通にトリュフ作ろっか 料理初心者でも失敗しないって本で書いてあったし…レッツクッキング!
|
|
|
|

|
◆目的 希望NPC:潮 綾(シナリオ『SWORD DANCER』他) で、NPCとお出かけ。 ※他の方とバッティング時の順番や演出はお任せします。 ◆行動 バレンタインを口実に綾の元を訪問。 東方(和風)系の文化の生まれ育ちのようだし、手作りチョコレートもあわせて和風にチョコ餅で。 (中身が生チョコの小さめの大福餅…初挑戦のため少々イビツ) 「和食以外慣れないって聞いたけど、これならどう? …まぁちょっと不揃いだけど」 (※料理自体は並にはできます。一応傭兵だし) で、本題。心身が大丈夫そうならお手合わせを。 「腕は訛ってない?じゃあ前の話…一勝負つきあって」 「まだ諦めてないわよ、綾やお父さんに追いつくって話!」
|
|
|
|
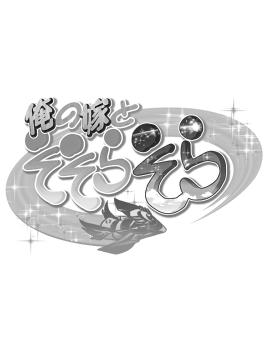
|
・フィール リン・ワーズワース少尉にチョコをたかりに行く。 英雄さんに祭り上げられてるし、きっとチョコもたくさん貰ってるはず。 え?チョコを誰かにあげないのかって?そんな余裕あったら自分で食べる! 今月の食費も大ピンチ。ここでチョコを貰えるかどうかで、今月の私の食料事情が変わる! 「リン少尉~、チョコ恵んでくださーい。また依頼受けにきますから!」 ・アルフォリス ほー、チョコが欲しいのかの?しょうがないのぅ、寂しい男共に貢がせればよかろう。どれ、ネットにチョコ募集の掲示板を立てるとするかの。 フィールにチョコを貢いだ者には、優先的にフィールのサービスシーンショット(写真)を買う権利をやるとしよう。
|
|
参加者一覧
リザルト
カレンダーの日付を見つめる。
バレンタイン、か。
バレンタインという祝祭には、千年以上の歴史があると言われている。
千年前といえばまだこの世界に『地上』があった頃ではないか。アビスから逃れ得た歴史書を紐解いても、うかがい知れるのは当時の伝承、しかもその概要だけだ。地上に暮らした人々がバレンタインの祝祭を、どんな風に過ごしていたのかは想像もつかない。まだウスバカゲロウの生態を説明するほうが、ずっと簡単かもしれないくらいだ。
けれどひとつ、わかることがあるとすればそれは、誰かが誰かを想う気持ちは、その頃からずっと、尊いものとされていたということだろう。
だからバレンタインデーは、世界が空に移ってもなお続いているのだ。
朝食のテーブルに座ってひとり、【羽奈瀬 リン】はそんなことを考えている。
銀のスプーンは手にしたままだ。半ば以上残っているフルーツヨーグルトの乳白色は、雪かぶった連峰のようにそこにとどまっている。
思い出が、点描画のように胸に蘇ってくる。
二十人が着席できる食卓は普段からずいぶん広いのだけど、今日はますます広大に、果てのない砂漠のように感じた。
「食べないの?」
席のひとつが埋まった。
でも椅子の背は引かれていない。着席する音すらしない。当然であろう、アニマの【スピカ】が姿を見せただけなのだから。
いや、とリンは答える。
「食べるよ。ちょっとぼんやりしてただけ」
言い訳のように匙を動かした。ふーん、とスピカは応じて、
「そういや今日、バレンタインデーだよね」
と告げた。リンがカレンダーを見ていたのに気がついたのだろうか。
「うん。バレンタインといえば」
リンの青い目に、淡い光沢がさした。
「昔、母様がバレンタインにクッキーを焼いてくれたなあ。僕と父様はこっそり扉の陰からのぞいて見てたんだ」
あの日のことを覚えている。盗み見の甘い気持ちも、バターが焼けクッキーが膨らんでいくときの、なんともくすぐったくなるような香りも覚えている。もちろん、その後食べたクッキーの歯触りも、何もかも。
懐かしそうな表情ね、とスピカは思った。
同時に、寂しそう、とも。
「ねえ、リン。じゃあ今日は」
「今日は?」
「クッキー作ってもらいましょう。理由? バレンタインだからいいの!」
「そんな急に……?」
と返しながらもリンは、乗り気になっている自分に気がついていた。
メイドたちは、スピカの申し出を了承した。
むしろ、日頃は実年齢以上の落ち着きと風格を見せる主(あるじ)が、急に本来の姿である子どもに戻ったようだと、これを喜んだのだった。
しかし一番はしゃいでいるのはスピカだろう。
「へええ、これがステンドグラスクッキー?」
と、メイドたちの周囲を巡り作業を見物しては、すごいすごいと声を上げる。
ステンドグラスクッキーとは、クッキーの生地に穴を開け、そこに砕いたキャンディーを入れて焼き上げたものを指す。一手間必要だけれど、その分、色鮮やかで目にも甘いお菓子となるのだ。
「リンのお母さんは、よくリンにこれを作ってくれたの?」
すると年かさのメイドが、いいえと首を振った。
「奥様は大変お忙しいかたで、料理をなさることは滅多にございませんでした」
でも、と彼女は言う。
「ですからその分、ごくまれに時間が取れたときはそれは熱心にお料理をされていましたよ」
ここで別のメイドが、そうそう、とうなずいた。彼女も随分昔からこの家に仕えている者だ。
「旦那様もお忙しくて、それでも奥様の誕生日には必ず、薔薇の花束を買っていらっしゃったものです」
「誕生日といえば、ぼっちゃまが生まれた翌年の……」
また別の、比較的若いもののベテランのメイドが参加した。
かくていっせいに昔話に花が咲いたのだった。
年季が浅い者であろうと、それどころか直接にリンの両親を知らない者であろうと、それぞれが直接目にした、あるいは伝え聞いた先代夫妻の話に参加するのである。嬉しげに、懐かしげに。
慕われていたんだね、とスピカは思った。誰も先代のことを悪く言わないからだ。それどころか自分の知っている逸話を語ること、共有することを楽しんでいるように見えた。
(いいなぁ……)
スピカは目を細めた。リンが今のリンなのは、両親あってのことなのだ。できることならば両親のことを見知って、リンがふたりから何を受け継いだのか、この目で確認してみたかった。
アニマのスピカは、クッキー作りに直接手をくだすことはできない。けれども焼き加減や穴に入れる飴の色を選んだりして、しっかり作業に参加した。
「飴の色は何がいいか? 赤、青……うーん迷っちゃうから全部!」
これを聞いてメイドたちは笑った。
「……っ、みんな笑わなくたっていいじゃない!」
わきあいあいと作業する楽しげな声に誘われて、いつしかリンもこの場を訪れていた。
「スピカ、飴、欲張りすぎ。でも綺麗なグラデーションになると思うよ」
「そう! グラデーション! 私が言いたかったのはそれだから!」
しばしの後、焼き上がったクッキーがリンの前の皿に置かれた。
なるほどまさしくグラデーション、一枚のクッキーの中に、赤からはじまる七色の飴が収まっている。ややはみ出し気味なのもご愛敬だ。
「ありがとう。いただくよ」
薫り高いティーカップを置き、リンはクッキーを口に運んだ。
「美味しかった」
リンの笑みは冬に見る木漏れ日のように、スピカの心を温かくする。
「どう? 少しは思い出の味がした?」
リンは笑顔のまま、首を横に振った。
「残念ながら母様の思い出のクッキーからは程遠いよ」
「そうなの?」
「うん。だって……塩が入ってたんだから!」
「し、お? それって美味しいの?」
いいや、とリンは声を上げて笑うのだった。
「気づいた母様は止めたけど、父様と飴の部分をなめながら食べたんだ」
懐かしい思い出だ。
「母様もクッキーは作れない人だったよ。でもあのときの記憶は、僕の中では『楽しい』のカテゴリに入ってる」
本当に感謝したい、とリンは言った。
「だってふたりが亡くなった後、こんな風に思い出話をする機会はなかったから」
はじめスピカは目を白黒させ、次にリンの言葉に微笑んで、そして、
「今日のこともまた、『楽しい』カテゴリの記憶として残ると思う」
と彼が告げたときには、うっすらと頬を染めたのである。
●
クローゼットに手をかける。さっと両側に開く。
ワックスがけした床に飛び込むように、目をなめらかに滑らせる。
あの服を掛けた場所は覚えているのだが、『探す』という行動に意味があると思う。
ハンガーに手を伸ばす。さっとつかむ。
ヘッドドレスまで含めた完全セット、これをまとう日が来たのだ。
エプロンドレスに袖を通す。待ってたよと言わんばかりに、服が肌を包み込んでくれるのを感じた。
いざや衣替えの刻(とき)、【アリシア・ストウフォース】はこれより、『メイドさんアリシア』へと変身を遂げる! みにくいあひるの子のは美しい白鳥に変身したが、もともとゴージャスなアリシアは、メイド衣装によって新たな魅力『可憐さ』を身につけるのだ!
「というわけで念願のメイド服を着てみましたっ! 似合う?」
アリシアは頬を桜色に染め、両手を重ねてお辞儀した。
「わー、ぱちぱちぱち!」
同じくメイド衣装のアニマ【ラビッツ】は、惜しみない拍手と歓声とついでに口で「ぱちぱち」と言う口喝采(?)をアリシアに送る。
「いやあ、いつか着ようと思っていたこの服、ようやく着る機会ができたよ」
「お菓子作りだもんね! たいぎめーぶん(大義名分)はあるよ!」
それにしても、と急にラビッツは腕組みする。
「アリシアが普通に料理する日がくるなんて……! 成長したんだね!」
照れくさげにアリシアは頬をかくと、材料の入った冷蔵庫を開けた。
「そりゃーワタシだってさあ、いつまでも料理できないでいいとは思ってなかったわけでねえ。バレンタインなんていい機会だから挑戦してみようとね……トリュフなら『料理初心者でも失敗しない』って本に書いてあったし」
なんて言いながらアリシアは、材料をひろげ最初の作業に入るのである。まな板に板チョコを置き、一生懸命に包丁で刻んでいく。
トリュフを選んだのは間違いじゃなかったね、とラビッツは思った。包丁を持つ手が危なっかしすぎる。おっかなびっくり、地雷原で踊っているかのような手つきではないか。腰も引けていた。作るのが簡単な料理でなければ、いまごろ大いなる悲劇が展開されていたかもしれない。
「ふぅ」
アリシアは額の汗をタオルで拭った。穏当な表現でも『がったがた』というほかない刻みっぷりとなったが、ともかくも負傷せず最初の作業は完遂できたのだ。これをボウルに入れるとつづけて、【ドーピングクッキング】に使う怪しい液薬をいそいそと取り出す。
つかまり立ちする赤ちゃんを眺めるような心境でラビッツはアリシアを見守っていた。
「アリシアがやる気になってくれて嬉しいよ。って、言ったそばからスキル使おうとしないでー!?」
「え?」
間一髪、最初の一滴が注がれる前に薬品投入は防がれた。瓶をもったままアリシアは動きを止めている。口をぽかんと開け、「手順、間違ってた?」と言うような表情を浮かべていた。
「『え?』じゃなくって!」
「チョコって健康にもいいらしいから、知り合いに配るのもありだなーって、そこから導き出された流れなんだけど」
「いやいやいや、それは元気になりすぎるから! 使わなくて大丈夫なんだよ!」
「いわば隠し味ということで」
えへへ、とアリシアは舌を出している。さすがにマズいかもと半分くらいは自覚していたようだ。
「そんな隠し味オススメできないから! 普通でいいの、ふつーで!」
はーい、と答えるとアリシアは作業に戻る。また何かやらかさないか――すでにラビッツの視線は、エッジの立った半月型に変化していた。
鍋に生クリームを入れ、火にかけ沸騰する程度まで温める……はずが、
「あ、ほらほらもう沸騰してるってば!」
もう黙って見ていられなくなり、ラビッツはコンロを指さしていた。とっくに生クリームは白いマグマ、ぶっくぶくのグツグツだ。
トラブルは続く。次はクリームをチョコに加えるところ。
「そっとね! そっと加え……わー! 入れすぎだよ-!」
チョコ入りのボウルが、あふれんほどのクリームにうずめられていた。
「これじゃ固まらないからー!」
と言っているそばから、「ならば」とアリシアは、余ったチョコを手で割りこれに加えていくのだった。
「チョコも適当に足さないで! チョコ撥ねてる!」
どうしてこうなるの……ラビッツは目を覆いたくなっていた。
翌日。
レーヴァティン軍【リン・ワーズワース】少尉は、彼女のトレードマークとなりつつある汚れたフライトジャケット姿で、颯爽とエスバイロから降り立った。くたびれたマフラーを引きあげて口元を隠す。カタパルトデッキでは彼女のマシンと入れ替わるようにして、次々と軍機が飛び立っていく。
「フットペダルが緩んでる。締めるからスパナ貸して」
クルーに手を伸ばすも、返ってきたのは「やっておきますから!」という整備兵からの威勢の良い返事だった。
「そう……じゃ、お願い」
ふっと微笑むと、リン少尉は飛行帽を手にしてぱんぱんと叩いた。砂埃がばらばらと舞い落ちる。六時間かぶりっぱなしだった帽子だ。普段もずっとそういう使い方をしているので、黒ずんでいるばかりかほうぼうほつれてもいる。縫わないとね、と思いながらこれを被り直した。このとき、
「少尉!」
呼びかける声があった。
さきほどの整備兵だろうか。リンは振り向いて、
「もえもえきゅんっ♪」
振り向いて……硬直した。
「……誰?」
「もえもえ……おっと、アリシア・ストウフォースであります!」
アリシアはブーツの踵をぴしゃっと合わせ敬礼した。メイドの格好で。
(ほら、少尉硬直しちゃってるじゃない……だからその服装で行くのは反対だったんだよ……まあ、いつもの無茶ぶりよりはましだけどー)
訥々とした口調でラビッツがつぶやいた。なお、ラビッツは現在プライベートモードである。
「あ、ああ。アリシアね。誰かと思った」
少尉とアリシアの頭上を横切った旗艦が、黒く長い影を投げかけた。
「少尉、今日はバレンタインデーだって知ってました!?」
「あー……そうみたいね」
「日頃の感謝の気持ちを込めて、不肖アリシア、トリュフを作ってきました!」
どうぞ! と彼女は包装した箱を差し出す。
「形は悪いかもしれませんし、混ぜ具合も不均一だったりしますが、えーと手作り菓子というのはですね、やはり心が大切だと……」
「大丈夫、おいしいよ」
と言ったときにはもう、リン少尉はチョコを一つほおばっていたのである。
「ありがとう」
●
「褒めてもらえて自信が持てました! じゃ、冒険でお世話になった仲間にも配ってきまーす!」
と勢いよく駆け出していったアリシアを見送り、リン・ワーズワースはまた歩き出す。
しかしすぐにまた呼び止められることになった。
「少尉! ほんの気持ちですが!」
さきほどの整備兵、十六才くらいの少女が、真っ赤な顔をして小箱をリン少尉に差し出したのだ。
「ありがとう。ハッピーバレンタイン」
受け取ってリンが短く告げると、整備兵は「キャー!」と歓声をあげて持ち場に戻っていく。
それからも自室に戻るまで、三度ほどリンは呼び止められた。そのたびにバックパックの中のチョコレートは増えていった。
自室のドアの前を見て、リンは小さく溜息をついた。ドアノブに袋がたくさん、それこそ鈴なりにぶら下げられていたのだ。中身は考えるまでもないだろう。
「……朝にあった分はぜんぶ部屋に入れたはずよね」
袋を提げて部屋に入る。
早朝からの勤務だったので疲れきっていたものの、もらったものは粗末にしたくないので、ひとつひとつ丁寧にテーブルの上に並べてゆく。
シャワーを浴びようと服を脱ぎかけたところでチャイムが鳴った。
「宅配便です」
と言う配達業者は、コンテナひとつ分くらいありそうな荷物を抱えていた。
ベッドの上にあぐらをかき、タオルを首にひっかけたTシャツ&短パン姿でリンは呆然としている。ちょっとしたチョコレート屋が開店できそうなほどの箱や袋が、彼女の目の前のテーブルにあった。もう置く場所が足りなくなり、デスクの上まで占拠されている。
「これ全部チョコレートだよね……鼻血出そう」
どうしたものか、とリンがつぶやいたとき、部屋のチャイムがまた鳴った。
「リン少尉~」
のぞき窓から見える姿は【フィール・ジュノ】だ。リンは唾を飲み込んだ。疲れを隠して微笑を浮かべる。
「どうかした?」
チョコレートを渡されるかと思いきや、実際は逆だった。
「チョコ恵んでくださーい。また依頼受けにきますから!」
リンは勢い込んでドアを開ける。
「それ本当!? くれるんじゃなくて!? というかフィールは誰かにあげたりしないの?」
「やだなあ、そんな余裕あったら自分で食べますよう」
うふふと笑うとフィールは手をひらひらと振った。
「なにせ今月の食費も大ピンチですもの。少尉のことだから、ひょっとしたら余ってるかぁと思って」
「余ってるというわけじゃないんだけど、もらってくれると……嬉しい」
自分のラフすぎる格好など忘れて、リンはフィールの手を引くようにして部屋に招き入れる。
(ふっふーん、予想的中♪)
アニマの【アルフォリス】だけに聞こえる声でフィールは呼びかける。
(急に少尉のところに行くとか言うから何かと思うたら……たくましいというか、ちゃっかりしとるというか)
透過度高めの幽霊のような姿で、アルフォリスは額に手を当てていた。
(なんとでも言って! ここでチョコをもらえるかどうかで、今月の私の食料事情は変わる!)
(おぬしはそこまでチョコ好きじゃったかのう)
(もちろん大好き! まあ、最近の食生活からすれば、塩と水のディナー以外ならなんでもウェルカムだけど!)
威張って言うことか、とアルフォリスは首をすくめた。
「ワーオ!」
部屋の様子を見るなりフィールは、誇張でなく心からの声を漏らしていた。
「むっちゃくちゃ多いじゃないですかー! さすが救国の英雄!」
デパートの『バレンタイン特設催しものコーナー』に迷い込んだのかと錯覚してしまった。
「茶化さないで。むしろこっちは、そういうのに祭り上げられて困惑してんだから……今から袋詰めするから待ってくれる?」
リンは黙々とパッケージを開け始めた。カカオの匂いがたちこめる。
それにしても世の中には、なんと多様のチョコがあるものか。トリュフ、ボンボン、生チョコにパイにガトーショコラ、一口サイズのプラリネもあれば、オレンジピールの薫り高いオランジェットもある。いわゆる板チョコことタブレットもあるし、バームクーヘンをチョコでコーティングした変わり種もあった。出どころだってやはりさまざま、高級店のもの、旅団限定のもの、観光地の名産品、それにもちろん手作りも!
「手伝いまーす!」
さっそく開封を手がけたフィールだったが、
「あ、メッセージカードや送り状は置いておいて。来月お返しをするから」
と少尉に言われ目を丸くした。
「少尉ってマメなんですねえ」
「もらいっぱなしってのが好かないだけよ」
「見習いたいものです」
「見習わなくていいって」
リン少尉の言葉が終わるやすかさず、アルフォリスがニヤリと注釈を入れる。
(見習いたくても、フィールの懐事情ではできんことじゃのう)
(誰のせいだと思ってんのよ!)
こうしてまんまとフィールが大量のチョコレートを収穫しているその背後では、アルフォリスがひそかな活動をはじめていた。
(フィールはチョコが大好きか……ふふ、しょうがないのぅ。せっかくじゃ、寂しい男どもに貢がせればよかろうて)
アニマのアルフォリスは単独でインターネットにアクセスできる。というか、しばしば単独アクセスして勝手にフィールの衣装をネット注文したりするので、フィールは常に金欠なのである。
しかしこのときアルフォリスが動いたのは、消費ではなく獲得のためだ。
アングラアイドルマニアが集うという裏サイトを立ち上げると、さっそくアルフォリスはこう書き込みを行った。
『【急募】グラマー魔法少女をチョコまみれにして遊ぼう。
トロットロに溶けたチョコ(※ホワイトでもブラックでも可)を、対象にぶちまけるだけの簡単なお仕事です。』
(ふむ、我ながら名キャッチコピーじゃのう)
さらにこう書き足す。
『成功報酬
チョコまみれになった魔法少女のあられもないデータ画像。』
『対象が大変な姿になるほど報酬画像も素晴らしい物となりますので、無闇にぶちまけるだけだと良い出来にはなりません。対象を芸術的にチョコで彩り、皆様でRー17的作品に仕上げましょう!』
書き込むだけでわくわくしてきた。我ってもしかして天才かもしれん――とほくそ笑みつつ、フィールのことを思ってアルフォリスはこう書き加えるのだった。
『なお、本人はぶちまけられたチョコをそのまま食べると思われるため、食用のみ可とします。』
いやあ、今夜が楽しみだ!
●
黄金の髪。淡い褐色の肌。透き通る青い瞳。
彼女は名を【フラジャイルのマリア】という。
マリアはこの世の存在ながら、この世にはないはずの存在だ。すなわち、とうに滅亡した地上文明の遺産『スレイブ』なのである。
マリアは自分のことを、鉄のスプーンを舐めるほどに味気ない『本機』という一人称で呼ぶ。しかし実際のところスレイブは、この名乗りからはむしろほど遠い、純魔法的な存在だ。彼女を構成するものはまだ、そのほとんどが解き明かされていない。
マリアがあえて機械じみた呼称を好むのは、意図的に魔法から遠ざかろうとしているからではあるまいか――そんなことを、ふと【メルフリート・グラストシェイド】は考えた。
「お待たせしました」
と現れたマリアは、飾り気のない白いコート姿である。襟の合わせ目からのぞくセーターも灰色、これではかつて、無菌室から外出できなかった頃の病院着と大差ないだろう。マリアはいつもこんな服装である。地味と呼ぶにも白すぎる。マリアの保護者であるドクター・リーウァイの趣味なのか、そもそもマリアが、色みの少ない服装が好みなのだろうか。
しかし白金色の髪、色白のメルフリートと並んで立てば、そんなマリアのモノトーン系の服装センスはぴたりと彼に似合うような気がして、そのことを思うたびメルフリートのアニマ【クー・コール・ロビン】は、なんとも複雑な心境になる……のだが、これは彼には秘密だ。
最近ときどきメルフリートは、こうしてマリアに会いに来ている。
ほぼ無菌室にこもりきりで無聊をかこつ彼女にそれなりの刺激を、という名目だが、メルフリート自身もマリアから、地上の記憶の断片など、なにか得るものはないかと思って通っているのが実際のところだ。
彼がマリアと過ごす時間はたいてい小半時程度だ。とりとめのない会話をしたり茶を付き合ったりする。本を貸してその一週間後に、その感想を聞くということもあった。最近ではマリアも、メルフリートとクーが訪れるのを楽しみにしているという。
「君の記憶の中にもバレンタインというイベントは存在したのか?」
その日メルフリートが、まず口にしたのはこの言葉だった。
小さな喫茶店、近ごろマリアを外出に誘うとき、メルフリートがよく利用する店だった。サイフォンで淹れる珈琲は知る人ぞ知る絶品だ。木目調のテーブルも、煉瓦の壁も、彼の趣味によく合った。
「あるのですか? 興味が」
おっとりした口調でマリアは首をかしげた。
ある、とメルフリートは答えた。
「今一つ由来がわからないものでな。そもそもチョコレートとは今のように菓子であったのか……保存性、携行性に優れ、カロリーの補給にも向くこの食べ物は元は戦場で食べられていたのではないだろうか」
このとき彼の前の小皿には、正方形した生チョコがひとつ乗っていた。珈琲と並ぶ店の名物だ。不均一な厚み、ココアパウダーがまぶされた表面、濃厚な茶色が、流水のような紋様を成している。
「実際僕も非常時に備えいくつか確保している。そう考えるとその由来にも何やら物騒な起源があるのではないのか、と思うのだ」
祈りを捧げるかのように、ぽん、とマリアは両手を合わせた。
「わかりました。メルフリート様は興味があるのですね? 地上時代の世界で、チョコレートという食物がどう扱われていたか、ということに。バレンタインにまつわる『愛』のテーマよりも?」
「あら、気づかなかった?」
クーが小さく笑った。
「メルフリートは食にはうるさいのよ。特に、甘いものにはね。なぜかうちのエスパイロには、いつも結構な数の甘味が積まれているんだから」
ふふ、とマリアも笑みを返す。
「この時代ではこう言うんですよね? 『色気より食い気』と」
「ありていに言ってしまえばそうなるな」
メルフリートは言った。少女以上大人未満の姿だが幼子のようなところがあるマリアから、『色気』という言葉が出てきたことにミスマッチを感じる。
「兎も角、食べ物は美味いほうがいいに決まっている」
それで、マリアは覚えているの? とクーは言う。
「千年前の世界では、バレンタインにおけるチョコレートはどう扱われていたのか。血生臭い由来があったのなら、愛がどうのというお話にはならない気がするのだけれど、ね」
「断片的な印象しかありません、本機には」
と前置きしたものの、メルフリートの予想以上に彼女はしっかりと語った。
「もっとずっと、高級なものだったはずです。少なくとも、一般の人がやすやすと口にできるものではなかった。そもそもチョコレートとは、『チョコの木』という特別な植物から取れる実だったはずです、直接に」
「カカオ豆を発酵させ、焙煎して作るものではなかった……?」
「ええ。この世界の人たちのようにかける必要はなかったはずです、手間を」
テレビでチョコレートの製法を見て、マリアは驚いたということだった。当時は『チョコの木』と呼ばれる希少植物から摂取できる『チョコの実』がそのままチョコレートだったというのである。
「実をそのままか……ただ、そのチョコの木は稀少品で大量生産・大量消費には向かなかったようだな」
「もちろん、もっと単純な、この飛空時代からすれば原型のような『チョコレート』はあったはずです。味はこの時代のものよりずっと落ちますが」
「とすれば、現代のほうが恵まれてるのかもね」
クーはしみじみと述べた。
空を見上げ素朴に憧れていたかつての時代と、空からアビスを見おろしては、いつか虚無に呑み込まれるだろうと怯える現代……その現代のほうが『恵まれている』と感じる瞬間はそうないようにクーは思う。
「今日はこれから街に、チョコレートを求めに行こうと思っている」
メルフリートは言って、テーブルの上にいくつもの冊子を広げる。様々な洋菓子店が発行しているバレンタインデー用のカタログ類だった。あざやかなチョコレート類がマリアの目を楽しませる。
「この時期は多様なチョコレートが売り出されるのでな。店によっては限定品などもある。買い集めるには人手がいるのだ……手伝いを頼みたい。どうだろうか?」
マリアが、この求めに二つ返事で応じたのは言うまでもない。
●
畳敷きの一室に、【ヴァニラビット・レプス】は通された。
壁には床の間と掛け軸。窓の前には障子。暖房らしいものは火鉢一つきりで、ひやりとした質感があったものの、ぴったりと襖が閉じられると空気は丸みを帯びる。
「楽にして」
と言った屋敷の主【潮 綾(うしお・あや)】は隙一つない和服姿でぴんと背筋を伸ばして華道の家元のごとく正座しており、いっこうに『楽に』している様子がない。こういう状況でどう『楽に』したらいいのか戸惑いヴァニラビットは、
「ええと……」
ぎこちなく綾の真似をして、膝を揃え畳についたのである。い草の肌触りは心地よかった。
(ヴァニラ、無理はしないほうがいいと思います)
写真が現像されるように音もなく、ヴァニラビットに並んで姿を見せたのは【EST-EX(イースター)】だった。といっても、ヴァニラビット以外には見えぬプライベートモードだが。
(その姿勢は、慣れていないと足が痺れることになるので)
「って言ったって……」
あぐらをかくのはさすがに、とヴァニラビットは小声で告げる。それにイースターだって正座してるじゃない、とも。
(私はイメージ映像ですから、いくら正座しても平気です。なんなら、この姿勢のまま空中浮遊だってできますよ)
「ちょ……気が散るから浮遊はやめてよね」
ところがイースターは、人形のようにすました顔でこれを聞き流すのだった。
落ち着かない様子のヴァニラビットから何か察したのか、
「卓袱(ちゃぶ)台を出すわ」
綾は立ち上がって、丸い板のようなものを運んできた。大型の盾? と思わず口にしかけたヴァニラビットは、すぐにその正体を理解する。
「ああ、折りたたみ式のテーブルね」
(もしかしてヴァニラ、あれを大型フリスビーと見間違ったのでは?)
「なんでよ」
とむくれつつも、実は当たらずも遠からずだけど、という思いはイースターには秘しておく。
ヴァニラビットが手伝ったこともあって、すぐに卓袱台テーブルはセッティングされた。これで足元が隠れることもあり、ヴァニラビットも安心して膝を崩すことができた。
助かった。ほんのわずかだが、もう足が痺れかけていた。
「今日はごめんね。いきなりおしかけちゃって」
「別にいいけど。でも本当に急だったんで、お茶くらいしか出せないから」
おや、と表情はそのままながら、イースターは唇の端をほんの1ミリだけ動かしていた。人嫌いというイメージがあった綾が、ヴァニラビットの突然の訪問に対し「別にいいけど」と言ったのだ。とすれば少し前に実施した、『ツーリング』という名の暴走交流はやる価値があったのだろう。
「いいのいいの。お茶菓子は用意してきたし……っていうか、お茶菓子こそが訪問の理由とも言えるし」
うふふと笑って、ヴァニラビットは机に紙箱を置いた。
「チョコレート、知ってる?」
「名前くらいは」
ほう、とヴァニラビットは口をアルファベットのO字型にした。
「おかしい?」
「いや、さすが東方文化を大事にしてる綾らしいと思っただけ。皮肉じゃないよ?」
「大事にしてるんじゃなくて、他を知らないだけだから」
自嘲気味に綾は言った。やはりだ、とイースターは思う。綾は前のときよりずっと、ツンケンした角が取れている。まあ、それでも扱いづらさはウニがタワシに変化した程度である。『愛想がいい』とはお世辞にも言えない。
「今日はチョコレートを一緒に食べる日なの」
「知ってる。伴天連(バテレン)タインなんとか、でしょ?」
「惜しい、『バレンタインデー』ね。まあ、地域によってはバテレンでもいいと思うけど」
(そのジョーク、真に受けられちゃったらどうするんです!)
今度はヴァニラビットがイースターの言葉を聞き流す番だった。
「ご覧あれ」
ヴァニラビットは箱を開けた。
そこに並んでいたのは、一口サイズの大福餅である。はんなりとして不揃い、少々いびつなものもある。
「和食以外慣れないって聞いたけど、これならどう? 中身が生チョコの大福、特製『チョコ餅』よ」
少なからず綾は虚を突かれた様子だ。
「これ、あなたが作ったの?」
きっ、と見上げた目線が鋭い。さすが剣鬼の娘……と、なぜかヴァニラビットは肌が粟立つのを覚えた。
「えーと、うん、そうね……初挑戦だったから見栄えはイマイチだけど。味は保証するわ」
作りながらさんざ味見したのでこれは確かである。傭兵稼業がそれなりに長くなってきたヴァニラビットだ。日常のことは一通りできる。
「……」
「安心して。毒は入ってないから」
「いや……毒じゃなくて……上手ね、と思って」
ヴァニラビットは内心ほっとした。綾が鋭い視線になったのは、彼女なりに感情を動かしたときの表情なのだろう。
「さあ、遠慮なく召し上がれ」
「いただくわ」
ひとつを手に取った綾は、
「……!」
やおら立ち上がった。
またも刃物のような眼差し!
殺られる!? ヴァニラビットは気迫を受けて瞬間、冷たい汗をかく。
しかし心配は無用。
「こんな美味しいものがこの世にあるなんて……!」
とつぶやくと、すとんと綾は座り直して、つくづくと大福を眺めたのである。まさに絶句、数秒ほどは言葉もない様子だった。ぱちくりとする目が潤んでいるようにも見える。
(買ったものを持ってこなくて良かったね。ヴァニラのチョコ大福でこんなに衝撃を受けているんだから、市販品だったら彼女、ショック死しちゃったかも)
などというイースターの憎まれ口も気にならない。ヴァニラビットは満面の笑みを浮かべていた。
「そんなに喜んでもらえて私も感激よ。上げるためにもってきたんだから、残りも食べちゃって」
すると綾は急に恥じ入ったように、うつむき加減でこう言った。
「ありがとう」
綾の新たな感覚を開いちゃったかもね、となんとなくヴァニラビットは思うのである。
ところで、とヴァニラビットは腰を浮かせつつ言う。
「その前に腹ごなしなんてどう?」
「どういう意味?」
「前の話……、一勝負つきあってほしいんだけど」
道場で汗を流さない? と切り出したのだ。
「まだ諦めてないわよ、綾やお父さんに追いつくって話!」
「……」
了承の意味だろう、綾は声も出さずふたたび立ち上がった。
彼女の目に、猛禽類のように『刺さる』光が宿っている。
やっぱり殺られる!? ヴァニラビットはまたまた冷たい汗をかく。
●
道場でひと稽古終えた後、綾はヴァニラビットと共に屋敷を出た。
綾は稽古着から、いくらか華やいだ和服に着替えている。
「あれ? 出かけるの?」
「人に誘われていて」
「もしかして……おデートとか?」
「買い物と食事に誘われているだけよ」
それをデートというのでは、とヴァニラビットは思ったが言わずにおいた。
ヴァニラビットと別れた綾は、交通機関を乗り継いで繁華街までたどり着いた。にぎやかな場所には来慣れていないので、駅舎の柱に隠れるようにする。
「時間ぴったりね」
来てくれたんだ、と【エクス・グラム】が告げる。
「断る理由、特になかったから」
語尾が跳ねるエクスとは対称的に、綾のほうは投げっぱなしのような口調だ。いわゆる利休バッグを両手で提げている。綾はちらちらと、柱の陰を伺っている様子だった。
するとまさにその場所から、
「すまない、急に呼び出して」
と【ブレイ・ユウガ】が顔を出した。
「……といっても、俺が知ったのも今日なんだが。知らない間にエクスが、勝手に連絡を取ってたんだってな」
「私は寿限無ちゃんに会いたかっただけよ」
とぼけた口調で、エクスは綾のアニマ【寿限無】の手を取った。もちろん実際に触れているわけではないが、手を取って引っ張り出すようにしたのである。
ブレイはうなずくも、その後はいくらか言葉を探すように、
「買い物と言っても大したものじゃないから、さっさと済ませよう」
などと言う。
駄目ねえ――エクスは内心腕組みしている。女心は風船のようなもの、しっかりつかんでおかないと飛んでいってしまうから、と、よっぽど言ってやろうかと思った。
しかし考え直し、エクスはこう言ってみる。
「ところでブレイ、彼女に言おうと思ってたことがあるんじゃなかった?」
「え? あ、ああ、そうだったな」
背中をどんと押された格好、さすがにブレイも言うほかなくなった。
「先日は、クリスマスパーティーに来てくれてありがとう。知らされてなかったから驚いた。楽しんでもらえたのなら嬉しい。それに、会えて良かった」
エクスがうながすように口を挟んだ。
「それだけ?」
「その……パーティで見た晴れ着、似合っていた。振り袖もいいものだな」
直球気味の表現だが、こういうときはド直球でいいとエクスは思い、こっそり親指を立てた。(それを寿限無が見て首をかしげている)
「あれは昔作ったもので……ああいう場に着ていく着物があれしかなかっただけよ。でも……まあ、褒め言葉として受け取っておくわ」
などと照れぎみに告げる綾を見て、エクスはますますニヤニヤとし、ブレイは目のやり場に困り、そして寿限無は、そんな彼らの様子を見上げてはきょとんとしているのだった。
ブレイが予約した店は、ホテルの高級割烹……ではなくファミリーレストランだった。仕方がないのだ、こういう店の知識がブレイにはまったくないのだから。背伸びして高級店にチャレンジしても、固くなってしまうだけだという自覚もあった。
それは綾も同じだったようで、彼女は席に着くと、
「あまり外食はしないのだけど」
とは言ったものの、緊張している様子はなかった。
「今はバレンタインフェアでチョコ系のデザートが安く食べられるから、好きな物を食べてほしい」
「ブレイ、いきなり『バレンタイン』と言う前に、綾にはその説明が必要だと思うけど」
とエクスが告げたのだが、大丈夫、とすぐに綾自身が返した。
「今日、ちょうどその伴天連もといバレンタインというのを経験してきたわ。手作りのチョコレートをもらって」
「おや!」
エクスは声を上げてしまう。なかなかどうして、綾は人気者ではないか。相手がどんな男か知らないが、手作りチョコとは恐れ入った! ブレイもうかうかしていると、綾をかっさらわれてしまうかもしれない。
でもブレイは平静だった。
「それはよかった」
と、綾がいい一日を過ごしていることを素直に喜んでいる。
「今日はじめて食べたんだけど、チョコレートって、なんというか……これまでの私の概念にはない菓子だった」
「それはいい意味?」
とブレイが置いたメニューの写真から、チョコケーキの写真を指して綾は言う。
「もちろん」
声が明るい。
物差しひとつ分くらいの間隔を保ったまま、夜なお明るい通りをブレイと綾が歩む。エクスと寿限無は、その後方をついて行く。
寿限無はその主とは対照的に、街が物珍しくて仕方ないらしい。きょろきょろ見回してはエクスに、あれはなに? これは? と問いかけている。
その一方でブレイと綾には会話が少ない、というのがエクスの分析だ。
もともと綾は無口なので、ブレイが話を振らないと答えない。なのにブレイは話題に詰まって、話しかけようとしてはやめてしまうということを繰り返していた。これを『初々しい』と好意的に表現することもできないではないが、長考に入ったチェスの指し手を見ているようで、エクスとしてはもどかしいことこの上なかった。
「ああ、ここだ」
ようやくブレイは、ある店を指さして声を上げた。
「エクスのオススメらしい装飾品店」
エクスが背後で、『エクスのオススメらしい』は言わなくていいの! と思っているとは夢にも思わない。
「装飾品に興味あるの?」
「いや、装飾品をつけた綾に興味がある」
ぽろりと言ってから、けっこう大胆なことを口にしたと気がつきブレイは怖じ気づく。「なにそれ?」「寒いこと言わないでくれる?」などネガティブな反応が数種類想像できた。
ところがそんなことはなかった。
「じゃ、じゃあちょっと試してみようか」
まんざらでもない様子で綾が答えたからだ。
小さくてシンプルな花の髪飾り、綾が選んだのはこれだった。豊かな黒髪に、椿のモチーフはよく映えた。
遠慮する綾に、
「せっかくのイベントだ、記念ということで受け取ってほしい」
と、はっきり告げてプレゼントすることができたのは、我ながら上出来だとブレイは思った。
必要ない、という綾に、「せめてこれくらいは」とブレイは告げ、彼女を屋敷まで送った。少々変なのが襲ってこようと、綾なら返り討ちにしてしまうだろうがそれはそれだ。名残惜しい気持ちはあった。綾も、特に拒まなかった。
「じゃあ、ここで」
門の前で振り返り、綾は告げた。
剣術道場を解散した今、武家屋敷風の広い邸宅に綾は一人で暮らしているという。
「そうだ」
いいことを思いついた、というように綾は言った。
「今日、もらったチョコ大福というのがあるのだけど、食べていく?」
「いや、やめておくよ。もう時間も遅い」
そんな時間に女性の一人暮らしの部屋に入るのはマナー違反だと思ったのだ。だから笑顔でブレイは手を振った。
「じゃあ、また」
「また」
そんな彼を見て溜息ついて、「まだまだねえ……」とエクスはつぶやいた。
依頼結果